レスポールは、ロックやブルースの名演を支えてきた名機です。しかし近年「レスポールは弾きにくい」「時代遅れではないか」と感じるギタリストも増えています。特に、ネックの太さやボディの重さが負担になりやすく、ハイポジションでの演奏が難しい点が欠点として挙げられます。
その影響もあり、レスポール弾きが減ったと感じる場面もあるでしょう。本記事では、レスポールとはどのようなギターなのかを再確認しつつ、弾きにくさを克服するためのポイントを解説します。
レスポールは本当に弾きにくいのか?

- レスポールとは?
- なぜ弾きにくいと言われるのか?
- 本当に時代遅れなのか?
- なぜ重い?
- レスポール弾きが減った理由
レスポールとは?
レスポールとは、ギブソン社が1952年に発売したエレキギターのモデルで、ロックやブルースを中心に幅広い音楽ジャンルで愛用されています。その特徴的なデザインとサウンドは、多くのギタリストに影響を与え、現在でも高い人気を誇っています。
レスポールの最大の特徴は、マホガニーとメイプルを組み合わせたボディにあります。マホガニー材がもたらす厚みのある低音と、メイプル材による明るく抜けの良い高音が絶妙にブレンドされ、独特のサステイン(音の伸び)を生み出します。また、ピックアップにはハムバッカーが採用されており、ノイズが少なく、太くパワフルなサウンドを実現しています。
構造面では、セットネック(ボディとネックが一体化した構造)が採用されており、これによってサステインが向上し、豊かな響きを持つ音が特徴となっています。しかし、同時にネックの調整が難しく、修理やメンテナンスに手間がかかるという側面もあります。
レスポールは、ジミー・ペイジ(Led Zeppelin)、スラッシュ(Guns N’ Roses)、エリック・クラプトンといった著名なギタリストによって使用されてきました。そのため、多くのプレイヤーが「ロックギターの象徴」として憧れるモデルでもあります。
一方で、レスポールには他のギターとは異なる独特の演奏感があり、「弾きにくい」と感じる人も少なくありません。その理由については、次の項目で詳しく解説していきます。
なぜ弾きにくいと言われるのか?
レスポールは多くのギタリストに愛されている一方で、「弾きにくい」と言われることがあります。その理由はいくつかあり、主に重量、ネックの太さ、ハイポジションのアクセスの難しさが挙げられます。
まず、重量が重いことが挙げられます。レスポールはマホガニーを主体としたボディ構造を持っているため、一般的に3.5kg~4.5kgほどの重さがあります。特に長時間の演奏では肩や腕に負担がかかりやすく、軽量なストラトキャスターやテレキャスターと比べると疲れを感じやすいです。
次に、ネックが太めであることも弾きにくさの一因です。レスポールのネックは、特に「50年代スタイル」と呼ばれるモデルではかなり厚みがあり、手の小さいギタリストにとっては握りづらいと感じることがあります。一方で、「60年代スタイル」のスリムなネックを採用したモデルも存在するため、ネックの形状を確認して自分に合うものを選ぶことが重要です。
さらに、ハイポジション(高音域)へのアクセスが難しい点も挙げられます。レスポールのボディ形状はシングルカッタウェイ(ボディのくびれが片側だけ)になっているため、フレット数の多い高音域での演奏時に手が届きにくくなります。これに対し、ストラトキャスターなどのダブルカッタウェイ構造を持つギターは、ハイフレットの操作がしやすい設計になっています。
このような理由から、レスポールは「弾きにくい」と言われることがあります。しかし、逆に言えば、その重量が生み出す豊かなサステインや、太いネックによる安定した演奏性は、レスポールならではの強みでもあります。そのため、自分のプレイスタイルに合わせて、メリットとデメリットを理解した上で選ぶことが大切です。
本当に時代遅れなのか?
レスポールが「時代遅れ」と言われることがありますが、実際にはそうとは言い切れません。確かに、現代の音楽シーンでは軽量なギターや多機能なモデリングギターが増え、多くのギタリストがストラトキャスターやスーパーストラト系のギターを選ぶ傾向にあります。しかし、レスポールが持つ独特のサウンドや演奏感は、現在でも多くのミュージシャンに支持されています。
レスポールの特徴は、太く甘いサステインのあるサウンドです。特にロックやブルースの分野では、この音色が求められる場面が多く、ギブソン・レスポールを愛用するプロギタリストも少なくありません。また、現代の音楽ジャンルにおいても、クラシックロックだけでなく、ハードロックやヘヴィメタル、ジャズなど幅広いジャンルで使用されています。
一方で、時代とともに求められるギターの性能も変化しています。たとえば、最近のギターは軽量化が進み、演奏の快適さが向上しています。さらに、ネックジョイントの改良や多彩なピックアップの搭載など、モダンな仕様のギターが増えています。そのため、レスポールの重さやハイポジションの弾きにくさをデメリットと感じる人がいるのも事実です。
しかし、これらの点を考慮しても、レスポールは決して「時代遅れ」と言えるものではありません。むしろ、伝統的なギターとしての価値が確立されており、今後も多くのギタリストに愛され続けるでしょう。特に、ヴィンテージレスポールの人気や、ギブソン社が新たに展開するモデルを見ても、その影響力は衰えていません。結局のところ、レスポールが時代遅れかどうかは、音楽のトレンドや個々の演奏スタイルによる部分が大きいのです。
なぜ重いのか?
レスポールが「重い」と言われる理由には、いくつかの要因があります。最も大きな要因は、使用されている木材です。レスポールのボディには主にマホガニーが使われており、トップ材にはメイプルが採用されています。マホガニーは音の厚みやサステインを生み出す一方で、密度が高く重量がある木材です。これが、レスポールが重くなる大きな理由の一つです。
加えて、レスポールのボディはソリッド構造で作られているため、ストラトキャスターやテレキャスターのような軽量なギターと比べると、質量が大きくなります。一部のモデルではチェンバードボディ(内部をくり抜いて軽量化した構造)が採用されていますが、それでも一般的なギターと比べると重量は重めです。
さらに、レスポールのヘッド角が深く、ネックも比較的太めに設計されているため、その分の重量が加わります。これはサウンドの厚みや独特の鳴りを生み出す要素でもありますが、長時間の演奏では肩や腰に負担を感じることがあるため、ストラップ選びや演奏姿勢に工夫が必要です。
このように、レスポールの重さはその構造や素材の特性によるものであり、音の厚みやサステインを生み出すために必要な要素とも言えます。そのため、軽量なギターと比べると取り回しが難しい部分はあるものの、重さがあるからこそ生まれるレスポール特有のサウンドは、多くのギタリストにとって魅力となっています。
レスポール弾きが減った理由
近年、レスポールを使用するギタリストが減ったと言われることがあります。その理由の一つとして、演奏性の問題が挙げられます。レスポールは重く、ハイポジションの演奏がしにくいため、特に速弾きやテクニカルなプレイを好むギタリストにとっては扱いづらいと感じることがあります。
また、現代の音楽シーンでは、多機能で汎用性の高いギターが求められることが多くなっています。例えば、ストラトキャスターやスーパーストラトといったギターは、軽量で取り回しがしやすく、ピックアップの組み合わせによって幅広い音作りが可能です。特に、アクティブピックアップを搭載したギターは、ハードロックやメタル系のジャンルで人気があり、速弾きを多用するプレイヤーにとっては利便性が高いと言えます。
さらに、価格の高さも一因となっています。ギブソン製のレスポールは高価であり、初心者や若いギタリストにとっては手が届きにくい存在です。エピフォン製のレスポールもありますが、価格帯や音の傾向を考慮すると、他のブランドのギターを選ぶ人も多くなっています。
また、音楽ジャンルの流行も影響しています。現在のポップスやロックでは、クリアでヌケの良いサウンドが好まれる傾向があり、シングルコイルやハムバッカーを搭載した軽量なギターが好まれることが多いです。そのため、レスポール特有の太く甘い音が求められる場面が減ってきているのも事実です。
しかし、レスポールが完全に廃れてしまったわけではありません。ブルース、ハードロック、ジャズなどのジャンルでは依然として愛用されており、レスポールならではのサウンドを求めるギタリストは今でも多く存在します。伝統的なギターとしての価値は変わらず、むしろヴィンテージ市場では高騰している傾向にあります。そのため、全体的にレスポール弾きが減ったと感じるかもしれませんが、レスポールの魅力が失われたわけではなく、単にギター市場のトレンドが変化しているだけだと言えるでしょう。
レスポールは本当に弾きにくいギターなのか?
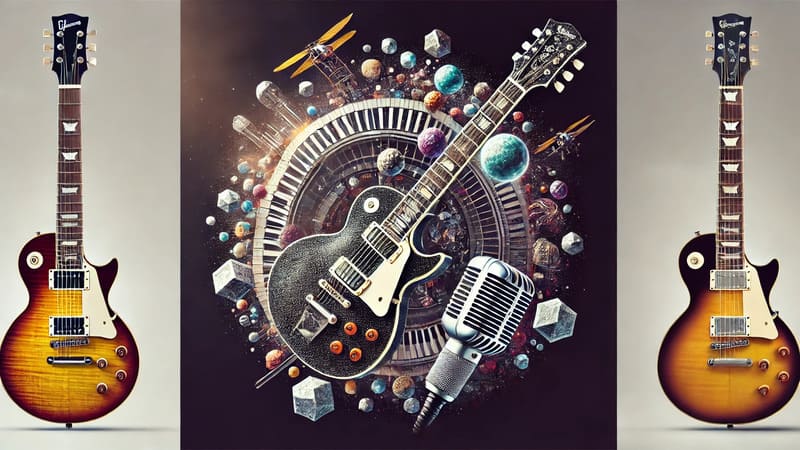
- レスポールは初心者でも弾きやすい?
- ハイポジションが弾きにくい理由
- ストラトとレスポールの弾きやすさ比較
- ハイフレットが弾きやすいギターとは?
- エピフォンのレスポールは弾きにくい?
レスポールは初心者でも弾きやすい?
レスポールは初心者でも弾けるギターではありますが、弾きやすいかどうかはプレイヤーの手の大きさや体格、演奏スタイルによって意見が分かれます。レスポールには独特の特徴があり、それがメリットにもデメリットにもなり得るため、初心者が選ぶ際には慎重に検討する必要があります。
まず、レスポールは比較的重量のあるギターです。一般的に4kg前後の重さがあり、長時間の演奏では肩や腰に負担がかかることがあります。特に体が小さい人や筋力が少ない人にとっては、立って演奏すると疲れやすく感じるかもしれません。これに対して、ストラトキャスターやテレキャスターのような軽量なギターは、初心者にとって扱いやすいという利点があります。
次に、ネックの形状についても考慮が必要です。レスポールのネックはモデルによって厚みが異なりますが、一般的に「ファットネック」と呼ばれる太めのものが多く採用されています。これにより、しっかりとした握り心地が得られますが、手が小さい人にとってはコードチェンジや速いフレーズの演奏が難しく感じることもあります。一方で、ネックが太い分、握り込むようなフィンガリングを多用するブルースやロックのプレイスタイルには向いているとも言えます。
また、レスポールのサウンドは初心者にも魅力的なポイントの一つです。ハムバッカーピックアップを搭載しているため、ノイズが少なく、太く力強い音を出しやすいのが特徴です。クリーンなトーンでも暖かみのあるサウンドが得られ、歪ませたときには厚みのあるロックな音が楽しめます。この点では、初心者でも扱いやすいギターと言えるでしょう。
ただし、レスポールはハイポジションの演奏がやや難しいというデメリットもあります。ボディとネックの接合部分(ヒール)が厚いため、17フレット以降の演奏がしにくく、特に手の小さい初心者にとってはストレスを感じることがあります。これに対して、ストラトキャスターやスーパーストラト系のギターはハイポジションのアクセスが良いため、速弾きや高音域のプレイを重視する人にはそちらの方が向いているかもしれません。
総合的に見ると、レスポールは初心者にとっても決して弾けないギターではありませんが、他のギターと比べるとやや扱いにくい部分もあるため、好みや体格に合わせた選択が重要になります。もしレスポールのサウンドに憧れがあるのであれば、軽量なモデルやネックが細めのタイプを選ぶと、初心者でも扱いやすくなるでしょう。また、実際に試奏をして、フィット感や弾きやすさを確認することも大切です。
ハイポジションが弾きにくい理由
レスポールがハイポジションで弾きにくいと言われる理由はいくつかありますが、最も大きな要因はネックとボディの接合部分(ヒール)の形状です。レスポールはセットネック構造を採用しており、ネックとボディが一体化しています。この構造によってサステインが豊かになり、独特の温かみのあるトーンを生み出すメリットがありますが、その一方で、ハイフレットの演奏がしづらくなるというデメリットもあります。
具体的には、レスポールのヒール部分は比較的大きく、ネックの裏側に厚みがあるため、17フレット以降になると手のひらがボディに当たりやすくなります。その結果、高音域のフレーズをスムーズに弾くことが難しくなり、速いパッセージやスライドがしづらいと感じることがあります。特に、小さな手のプレイヤーにとっては、この点が大きなハードルになることもあります。
さらに、ネックのジョイント部分が深いため、ストラトキャスターやスーパーストラトのようにハイフレットへのアクセスを意識したデザインとは異なり、指板の奥まで手を伸ばしにくい構造になっています。そのため、ハイポジションでのプレイが多い音楽ジャンル、たとえば速弾きやテクニカルなギタープレイを好むギタリストにとっては、レスポールの構造が不便に感じられることがあるでしょう。
とはいえ、レスポールのハイポジションの弾きにくさを克服する方法もあります。例えば、クラシックな持ち方ではなく、親指をネック裏にしっかりと置きながら手首を柔軟に使うことで、ハイフレットでの動きをスムーズにすることが可能です。また、レスポールの中にはカッタウェイの深いモデルや、モダンな仕様でヒールカットが施されたモデルも存在するため、ハイポジションを多用するプレイヤーはそうしたギターを選ぶのも一つの手段です。
ストラトとレスポールの弾きやすさ比較
ストラトキャスターとレスポールは、どちらも人気の高いギターですが、弾きやすさには大きな違いがあります。それぞれの構造や特徴を比較することで、自分に合ったギターを見つける手助けになるでしょう。
まず、ネックの形状に注目すると、ストラトキャスターのネックは細めで握りやすく、特にモダンなCシェイプやスリムネック仕様のモデルは、速弾きや細かいフィンガリングがしやすい設計になっています。一方、レスポールのネックは比較的厚みがあり、特に1950年代のレスポールに見られる「ファットネック」モデルは、しっかりとしたグリップ感が特徴です。これにより、パワフルなコードストロークやブルージーなプレイには適していますが、細かい運指が必要なプレイではストラトの方が優位に感じることもあります。
また、ボディの形状も弾きやすさに影響します。ストラトキャスターはコンター加工が施されており、体にフィットするようにデザインされています。これにより、立って弾くときだけでなく、座っての演奏でも快適に感じられます。一方で、レスポールはフラットなボディ構造のため、長時間の演奏では疲れやすいと感じることがあるかもしれません。
ハイポジションのアクセスに関しては、ストラトキャスターの方が圧倒的に優れています。ストラトはボルトオンネック構造であり、ジョイント部分のヒールが小さく、カッタウェイが深いため、22フレット付近でもスムーズに演奏できます。対して、レスポールはセットネック構造で、ヒール部分が厚くなっているため、高音域での演奏がやや制限される傾向にあります。
総合的に見ると、ストラトキャスターは軽量で弾きやすく、幅広いジャンルに対応できるギターであるのに対し、レスポールは重量感があるものの、サウンドの厚みや豊かなサステインが魅力です。それぞれの特性を理解した上で、プレイスタイルに合ったギターを選ぶことが大切です。
ハイフレットが弾きやすいギターとは?
ハイフレットが弾きやすいギターには、いくつかの共通した特徴があります。最も重要なのは、ネックジョイント部分の設計とカッタウェイの形状です。
まず、ハイフレットでの演奏を重視するギターでは、ヒールレス加工が施されていることが多いです。例えば、Ibanez(アイバニーズ)やJackson(ジャクソン)などのスーパーストラト系のギターは、ヒール部分が滑らかにカットされており、20フレット以上の演奏がしやすくなっています。
また、ダブルカッタウェイ構造のギターは、ハイフレットへのアクセスが容易です。ストラトキャスターのように、深くえぐられたボディデザインは、高音域を多用するギタリストにとって大きなメリットとなります。さらに、PRS(ポール・リード・スミス)などのギターは、セットネックながらもヒール部分を工夫し、ハイフレットの演奏性を向上させています。
加えて、ネックの薄さや指板のR(カーブ)の違いも影響します。フラットな指板を持つギターは、ハイフレットでも押弦しやすく、速弾きやスウィープ奏法に向いています。これらの要素を考慮しながら、自分に合ったギターを選ぶと良いでしょう。
エピフォンのレスポールは弾きにくい?
エピフォンのレスポールは、ギブソンのレスポールと比べて弾きにくいと言われることがあります。その理由として、ネックの形状、木材の違い、重量バランスなどが影響しています。
まず、エピフォンのレスポールは、ギブソンのものよりネックがやや太めで、手が小さいプレイヤーには握りづらいと感じることがあります。また、仕上げの精度がギブソンに比べて劣ることがあり、フレットのエッジが若干粗い個体も存在します。これにより、スムーズな運指がしにくいと感じることもあります。
ただし、近年のエピフォンの品質は向上しており、モデルによってはギブソンと遜色ないものもあります。特に「Inspired by Gibson」シリーズは、ギブソンの仕様を忠実に再現しており、演奏性も向上しています。
結論として、エピフォンのレスポールが弾きにくいかどうかは、個人の好みやモデルによる部分が大きいです。試奏をして、自分に合ったものを選ぶことが大切です。


