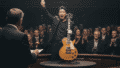「ギターやめたほうがいいのかな…」と、楽器を手に取るたびに心が揺らいでいませんか。
憧れの曲を弾く日を夢見て始めたものの、現実は想像以上に厳しく、上手くならない自分に嫌気がさしているかもしれません。実は、その悩みはあなた一人だけのものではありません。
驚くことに、ギター初心者の9割が挫折するというデータもあるほど、継続は難しいのが現実です。多くの方が、まるで無理ゲーのように感じる壁にぶつかり、具体的なやめた理由を抱えてギターから離れていきます。
上達しないまま10年が過ぎてしまう可能性や、いつしかギターが趣味だと公言するのが恥ずかしいと感じる心理も、決して他人事ではないのです。
この記事では、あなたが抱える「ギター やめたほうがいい」という切実な悩みに寄り添い、多くの人が挫折する根本的な原因を深掘りします。
さらに、やめるという決断を下す前に試すべき具体的な対策や、後悔しないための判断基準を網羅的に解説します。この記事を読めば、ギターとの向き合い方が明確になり、あなたにとって最良の選択をするためのヒントがきっと見つかるはずです。
ギターはやめたほうがいいと感じる主な原因
- 9割が挫折、すぐやめるのはなぜ?
- みんなのギターをやめた理由とは
- 上手くならないまま10年経つことも
- ギターは無理ゲー?挫折ポイント
- ギターが趣味は恥ずかしいと感じる心理
9割が挫折、すぐやめるのはなぜ?
ギターという楽器が持つ華やかなイメージとは裏腹に、その継続がいかに困難であるかは、衝撃的なデータによって示されています。
大手ギターメーカーであるフェンダー社が過去に行った調査では「ギターを始めた人の約9割が1年以内に演奏をやめてしまう」という結果が明らかになりました(参照:フェンダー社によると、ギター初心者の90%は1年以内に辞めてしまう。)
では、なぜこれほど多くの人が短期間でギターから離れてしまうのでしょうか。その根底には、初心者が演奏の楽しさを実感する前に直面する、いくつかの共通した壁の存在が考えられます。
物理的な苦痛:指先の痛み
最も直接的で避けがたい壁が、指先の痛みです。特にアコースティックギターの金属弦は硬く、弦を押さえる指先には相当な圧力がかかります。
練習を始めるとすぐに指先が赤く腫れ、ひどい場合は水ぶくれができてしまいます。この痛みに耐え、指先の皮が硬い「指タコ」が形成されるまでには、ある程度の期間、痛みを伴う練習を続ける必要があります。
この最初の物理的な苦痛に耐えきれず、練習そのものが億劫になってしまうのです。
技術的な最初の壁:Fコードの存在
技術面で初心者が直面する最大の壁が、通称「Fコード」に代表されるバレーコード(セーハ)です。これは、1本の指(主に人差し指)で複数の弦を同時に押さえる奏法で、綺麗な音を出すには相応の握力とコツが求められます。
多くの楽曲で頻繁に使用されるため、このコードが弾けないと演奏できる曲の幅が著しく制限されます。弾きたい曲が弾けない、練習しても音が出ないという状況が続くことで、達成感を得られずにモチベーションが低下し、挫折へとつながるケースが後を絶ちません。
これらの初期段階で現れるハードルが、多くの初心者からギターを弾く喜びを奪い、9割もの人々がギターから離れてしまう大きな要因となっています。
みんなのギターをやめた理由とは
前述の通り、指の痛みやFコードの壁は多くの初心者が挫折する共通の理由ですが、ギターをやめてしまう理由はそれだけではありません。練習をある程度続けていく中で、さまざまな現実的な問題や心理的な障壁に直面し、継続を断念するケースも少なくありません。
モチベーションの喪失
一つの大きな理由として、モチベーションの低下が挙げられます。「文化祭でライブを成功させる」「好きなアーティストの曲を1曲マスターする」といった具体的な目標を達成した後に、次の目標を見つけられずに燃え尽きてしまうことがあります。
明確な目標がないまま練習を続けるのは精神的に難しく、次第にギターに触れる時間が減ってしまうのです。
練習の単調さと時間の確保
好きな曲を華麗に弾きこなすためには、地道な基礎練習の繰り返しが不可欠です。しかし、この基礎練習に面白みを見出せず、単調な作業だと感じて飽きてしまう人もいます。
また、特に社会人になってからギターを始めた場合、仕事や家庭の都合で安定した練習時間を確保することが難しくなります。練習時間が取れないことで上達が遅れ、それがさらなるモチベーション低下を招くという悪循環に陥ってしまうのです。
音楽仲間や発表の場の不在
独学で一人黙々と練習していると、自分の成長を客観的に評価することが難しく、行き詰まったときに相談できる相手もいません。共に練習する仲間や、練習の成果を披露する場がないことは、孤独感を深め、継続の意欲を削ぐ原因となります。
生活への支障
まれなケースですが、ギターにのめり込むあまり、学業や仕事、家族との時間といった他の大切な事柄がおろそかになってしまうこともあります。趣味が生活に悪影響を及ぼし始めると、罪悪感からギターを楽しむことができなくなり、やめるという選択に至ることも考えられます。
これらの多様な理由が複雑に絡み合い、多くの人が愛着を持って手にしたはずのギターを、手放すという決断を下しているのです。
上手くならないまま10年経つことも
「継続は力なり」という言葉は真実ですが、ただ時間をかければ誰もがプロのように上達するわけではありません。中には、「ギターを始めて10年経つのに、一向に上達しない」と深刻に悩む人も存在します。
長期間にわたって上達が停滞してしまう背景には、練習の「量」ではなく「質」に関する問題が潜んでいることがほとんどです。
非効率な練習の繰り返し
最も大きな要因は、練習方法そのものにあります。ただ漠然と好きな曲を弾いているだけでは、効率的なスキルアップは望めません。例えば、自分の演奏を録音して客観的に聴き直すことなく、同じ間違いを無意識に繰り返しているケースです。
また、苦手なコードチェンジやリズムパターンから逃げ、自分が弾きやすいフレーズばかりを練習していては、総合的な演奏能力は向上しにくいでしょう。
身体の使い方の問題
ギター演奏は、指先の力だけで行うものではなく、手首や腕、肩、そして体幹に至るまで、全身を効率的に使うことで成り立っています。不必要な力みや不自然なフォームで弾き続けていると、上達が遅れるだけでなく、腱鞘炎など身体を痛める原因にもなりかねません。
多くの人は、自分がどのように身体を使っているかを意識しておらず、上達を妨げる癖がついてしまっていることに気づいていません。
理論的な理解の欠如
なぜその音が鳴るのか、なぜそのコードが心地よく響くのかといった音楽理論の基礎を理解しないまま、ただタブ譜の数字を追うだけの練習に終始していると、応用力が身につきません。
理論的な裏付けがないため、新しい曲に取り組むたびにゼロから覚え直す必要があり、成長のスピードが著しく遅くなってしまいます。
これらの点から、がむしゃらに時間を費やすだけでは、10年経っても初心者レベルから抜け出せないという状況に陥る可能性があります。上達のためには、常に自分の練習方法を客観的に見つめ直し、改善していく視点が不可欠です。
ギターは無理ゲー?挫折ポイント
ギターが「無理ゲー」だと感じてしまうのには、初心者が特に陥りやすい、いくつかの共通した「挫折ポイント」が存在します。これらのポイントを事前に知っておくことで、心の準備ができ、対策を講じることが可能になります。
| 主な挫折ポイント | 内容と心理的影響 | 対策の方向性 |
| Fコードの壁 | 何度練習しても綺麗な音が出ず、「自分には才能がない」と思い込んでしまう。多くの曲で必要とされるため、ここで進行が完全にストップしやすい。 | Fコードの簡易版(省略コード)から試す。握力を鍛える器具を使う。ギター教室で正しい押さえ方のコツを教わる。 |
| いきなり難しい曲への挑戦 | 憧れのアーティストの複雑な曲に挑戦し、全く弾けない現実に直面して自信を喪失する。理想と現実のギャップに心が折れてしまう。 | まずはコードが4つ程度で構成される簡単な曲から始める。「1曲弾ききれた」という成功体験を積み重ねることが大切。 |
| 出来不出来の波 | 「昨日は弾けたフレーズが今日は弾けない」という日々のコンディションの波に一喜一憂し、精神的に疲弊する。成長が実感できず、練習が苦痛になる。 | 弾けない日は無理せず、テンポを落として練習するか、基礎練習に切り替える。一日休んで心身をリフレッシュすることも有効。 |
| 練習の単調さ | クロマチックスケールやコードチェンジといった基礎練習ばかりで、音楽を演奏している実感が得られず飽きてしまう。 | 基礎練習と好きな曲の練習をバランス良く組み合わせる。練習時間を15分など短く区切り、集中力を維持する。 |
このように、多くの初心者が同じようなポイントでつまづいています。大切なのは、これらが誰にでも起こりうる自然な過程であると理解し、「無理ゲーだ」と諦めてしまう前に、一つ一つの壁に対して適切なアプローチを試してみることです。
ギターが趣味は恥ずかしいと感じる心理
意外に思われるかもしれませんが、「ギターが趣味」であることを、どこか恥ずかしいと感じてしまう人が一定数存在します。この心理は、特に上達が思うように進んでいないと感じている場合に顕著になります。
理想と現実のギャップ
ギターという楽器には、「弾けたらカッコいい」という華やかなパブリックイメージがあります。そのため、友人や知人に「趣味はギターです」と公言すると、周囲からはある程度の演奏レベルを期待されることがあります。
しかし、実際には簡単な曲もおぼつかない自分の実力との間に大きなギャップがあり、その期待に応えられないことへのプレッシャーや引け目から、「趣味だと言うのが恥ずかしい」と感じてしまうのです。
披露する場がなく比較対象もいない孤独感
一人で黙々と練習していると、自分のレベルがどの程度なのか客観的に判断できません。上達しているのかどうかも分からず、自信が持てないまま時間だけが過ぎていきます。
練習の成果を披露する場もなく、誰からもフィードバックを得られない状況は、次第に孤独感を深めます。「こんなレベルでは、とても人前で弾けるものではない」という思いが強まり、趣味であることを隠したくなってしまうのです。
「いつまで初心者なんだ」という自己嫌悪
ギターを始めてから年月が経っているにもかかわらず、いつまでも初心者の域を脱せないでいると、「自分は才能がないのではないか」「時間を無駄にしているのではないか」といった自己嫌悪に陥ることがあります。
このネガティブな感情が、「こんな状態でギターが趣味だなんて、恥ずかしくて言えない」という心理につながっていきます。
このように、技術的な問題だけでなく、他者との比較や自己評価といった心理的な側面も、ギターを続ける上での隠れた障壁となり得るのです。
ギターはやめたほうがいいと決断する前に
- 具体的な目標設定が継続のコツ
- 練習方法の見直しで壁を乗り越える
- 音楽仲間や教室がモチベーションに
- ギター自体の状態を確認してみよう
- 一時的にギターから離れてみる選択肢
- 「ギターはやめたほうがいい」か最終判断
具体的な目標設定が継続のコツ
もしあなたが「ギターをやめようか」と考えているなら、その決断を下す前に、一度ご自身の目標を振り返ってみてください。
漠然と「上手くなりたい」と思っているだけでは、日々の練習のモチベーションを維持するのは非常に困難です。明確で具体的な目標を設定することが、挫折の淵から抜け出すための最も効果的な方法の一つとなります。
目標は、壮大である必要はありません。むしろ、少し頑張れば達成できそうな、現実的なものを設定することが鍵となります。
短期的な目標の例
- 1週間以内に、CコードとGコードのチェンジをスムーズにできるようにする
- 1ヶ月以内に、好きな曲のイントロ部分だけでも弾けるようにする
- 次の週末に、自分の演奏を初めて録音して聴いてみる
中長期的な目標の例
- 3ヶ月後の友人の誕生日に、弾き語りで1曲プレゼントする
- 半年後の発表会やオープンマイクイベントに出演する
- 1年以内に、憧れのアーティストの曲を1曲完全にコピーする
このように、期間と達成基準が明確な目標を設定することで、日々の練習に目的意識が生まれます。「今日はこのフレーズをマスターしよう」というように、練習が「やらなければいけない作業」から「目標達成のためのステップ」に変わるのです。
一つの目標をクリアすれば、それが成功体験となり、大きな自信につながります。そして、その自信が次のより高い目標に挑戦する意欲を生み出します。やめることを考える前に、まずは達成可能な小さな目標を立て、それをクリアする喜びを味わってみることを強くお勧めします。
練習方法の見直しで壁を乗り越える
「毎日練習しているのに、全く上達しない」と感じる場合、その原因は練習の「量」ではなく「質」にある可能性が高いです。がむしゃらに同じことを繰り返すのではなく、一度立ち止まって練習方法そのものを見直すことで、停滞していた状況を打破できるかもしれません。
メトロノームの活用
自己流の練習で最も陥りやすいのが、リズム感の欠如です。自分では弾けているつもりでも、リズムが不安定では演奏として成立しません。メトロノームを使い、最初はゆっくりとしたテンポで正確に弾く練習を徹底してください。
一音一音を丁寧に出すことを意識することで、指の動きが安定し、結果的に速いフレーズも綺麗に弾けるようになります。
できない部分の集中練習
曲を練習する際、最初から最後まで通して弾くことばかりに固執していませんか。それでは、自分が苦手な箇所を何度も間違えるだけで、効率的な上達は望めません。
弾けないコードチェンジや特定のフレーズだけを抜き出し、そこだけを繰り返し練習する「部分練習」を取り入れましょう。苦手な部分を克服できれば、曲全体の完成度は飛躍的に向上します。
自分の演奏を録音して聴く
客観的な視点を持つことは、上達への近道です。スマートフォンなどで自分の演奏を録音し、それを聴き返してみてください。
弾いている最中には気づかなかったリズムのズレや音の濁りなど、改善すべき点が明確に分かるはずです。自分の弱点を正確に把握することが、質の高い練習の第一歩となります。
これらの練習方法の見直しは、地味で根気がいる作業かもしれません。しかし、ただ時間を浪費するだけの練習から脱却し、着実に成長を実感するためには不可欠なプロセスです。やめるという結論を出す前に、一度、練習の質を高める工夫を試してみてはいかがでしょうか。
音楽仲間や教室がモチベーションに
独学でのギター練習は、自由である一方、孤独に陥りやすいという大きなデメリットがあります。行き詰まったときに相談する相手がおらず、モチベーションを維持するのが難しいと感じたら、外部とのつながりを持つことを検討してみましょう。
音楽仲間やギター教室の存在は、あなたのギターライフを劇的に変える可能性があります。
音楽仲間の効果
同じようにギターを練習している仲間がいれば、お互いに情報交換をしたり、励まし合ったりすることができます。「あの曲、どうやって弾いてる?」「最近、練習してる?」といった何気ない会話が、孤独感を和らげ、再びギターに向かうきっかけを与えてくれます。
また、仲間と一緒にセッション(合奏)する機会を持てば、一人で弾くのとは全く違う、音楽の本当の楽しさを実感できるでしょう。音楽教室や地域のサークル、SNSなどを通じて仲間を探すことができます。
ギター教室に通うメリット
もし経済的に許されるのであれば、ギター教室に通うのは最も確実な上達方法の一つです。プロの講師から指導を受けることで、自己流では気づけなかったフォームの癖や非効率な練習方法を的確に修正してもらえます。
Fコードのような技術的な壁も、正しいコツを教わることで、案外あっさりと乗り越えられるかもしれません。
さらに、多くの音楽教室では定期的に発表会などのイベントが開催されます。こうした「披露する場」があることは、練習に対する強力な動機付けとなります。「次の発表会であの曲を弾く」という明確な目標ができれば、日々の練習にも身が入るはずです。
一人で抱え込まず、外部の力を借りることで、ギターの練習は苦しいものから楽しいものへと変わる可能性があります。やめるという選択は、これらの選択肢を試してからでも遅くはないでしょう。
ギター自体の状態を確認してみよう
「どうしても上手く弾けない」という悩みの原因が、あなたの技術や練習方法だけにあるとは限りません。特に、初心者向けの安価なギターや、長年メンテナンスされていないギターを使用している場合、楽器自体が弾きにくい状態になっている可能性があります。
やめる決断をする前に、一度、ご自身のギターの状態を専門家に見てもらうことをお勧めします。
弦高は適切か?
「弦高(げんこう)」とは、指板と弦の間の隙間のことです。この弦高が高すぎると、弦を押さえるのに余計な力が必要になり、指がすぐに痛くなってしまいます。
Fコードのようなバレーコードが特に押さえにくく感じられる場合、弦高が高すぎることが原因かもしれません。逆に低すぎても、弦がフレットに触れてしまい「ビビり」というノイズが発生します。適切な弦高に調整するだけで、驚くほどギターが弾きやすくなることがあります。
ネックは反っていないか?
ギターのネックは、木材でできているため、湿度や温度の変化によって反ってしまうことがあります。ネックが反ると弦高が変化し、演奏性に大きな影響を与えます。これもまた、弾きにくさや音の異常の原因となります。
フレットやナットの状態は?
フレット(指板に打ち込まれた金属の棒)が錆びていたり、摩耗してすり減っていたりすると、チョーキングなどの奏法がしにくくなったり、音程が不安定になったりします。また、弦を支えるナットの溝が適切でない場合も、押さえにくさやチューニングの狂いにつながります。
これらのチェックや調整は、専門的な知識が必要です。もし心当たりがあれば、楽器店にギターを持ち込んで、専門のスタッフに点検・調整を依頼してみてください。数千円程度の調整費用で、あなたのギターが「無理ゲー」から「弾きやすい最高のパートナー」に生まれ変わる可能性も十分にあります。
一時的にギターから離れてみる選択肢
練習が辛い、ギターを見るのも嫌だ。もし、あなたがそこまで追い詰められているのであれば、無理に続ける必要はありません。一度、意図的にギターから離れてみる、というのも有効な選択肢の一つです。これは「やめる」という最終決断ではなく、あくまで「戦略的な休憩」です。
義務感や焦りから解放され、ギターのない生活を送ることで、心身ともにリフレッシュすることができます。
毎日「練習しなければ」というプレッシャーにさらされている状態では、音楽を楽しむ余裕は生まれません。数週間、あるいは数ヶ月間ギターに一切触れないことで、そのプレッシャーから解放されるのです。
この休憩期間中に、不思議な現象が起こることがあります。一つは、脳内で情報が整理されることです。練習中に無我夢中で詰め込んだ指の動きや音楽理論が、睡眠や他の活動を通じて、無意識のうちに整理・定着することがあります。
そして、久しぶりにギターを手に取ったとき、「以前はできなかったフレーズがなぜか弾けるようになっている」という経験をすることがあるのです。
もう一つの効果は、音楽への情熱を再確認できることです。ギターから離れて、純粋に一人のリスナーとしてさまざまな音楽を聴いているうちに、「やっぱりあの曲を弾いてみたい」「ギターの音が恋しい」という自然な感情が再び湧き上がってくるかもしれません。
誰かに強制されるのではなく、自分自身の内側から湧き出る「弾きたい」という気持ちこそが、最も強力なモチベーションとなります。
もし、休憩してもギターに戻りたいと思わなければ、その時が本当にやめるべきタイミングなのかもしれません。しかし、辛い気持ちのまま無理やり練習を続けるよりも、一度距離を置くことで、より良い形でギターと再び向き合える可能性が高まるのです。
「ギターはやめたほうがいい」か最終判断
- ギター初心者の約9割は1年以内に挫折するという現実がある
- 挫折の主な初期原因は「指先の痛み」と「Fコードの壁」
- 目標達成後の燃え尽きなど「モチベーションの低下」も大きな理由
- 練習時間の確保の難しさや、練習の単調さも継続を困難にする
- 独学の孤独感や、成果を披露する場がないことも意欲を削ぐ
- 練習の「量」だけでなく「質」が低いために上達が停滞することがある
- 非効率な練習を続けると10年経っても上手くならない可能性も
- 無理ゲーと感じる挫折ポイントには、簡易コードなど具体的な対策がある
- 上達しないことで「ギターが趣味」と言うのが恥ずかしくなる心理もある
- やめる前に、具体的で達成可能な目標を再設定してみる
- メトロノーム活用や部分練習など、練習方法の見直しを試みる
- 音楽仲間やギター教室とのつながりが、強力なモチベーションになる
- 弾きにくさの原因が、弦高などギター自体の状態にある場合も
- 辛い時は無理せず、一時的にギターから離れてみるのも有効な手段
- 最終的に「楽しい」と感じるかどうかが最も大切な判断基準