ギターを弾いていると、突然弦が切れることがあります。初めて経験すると驚くだけでなく、怪我をするのではないかと怖いと感じる人も多いでしょう。
実は、弦が切れる前には前兆があり、切れる場所や切れる理由を知っておくことで対策ができます。弦が頻繁に切れると「弾き方が下手なのか」と不安になることもあるが、正しいメンテナンスをすれば寿命を延ばし、切れにくくする方法もあります。本記事では、弦が切れる原因や直し方について詳しく解説します。
ギターの弦が切れる原因と対策
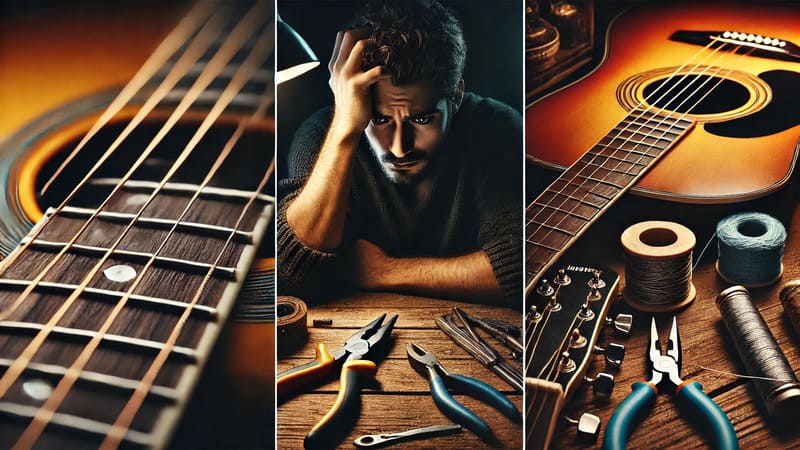
- ギターの弦が切れる前兆とは?
- ギターの弦が切れる主な理由
- どこが切れやすい?弦が切れる場所の特徴
- 弦が切れるのが怖い…怪我のリスクは?
- ギター初心者は弦を切りやすい?下手だから?
ギターの弦が切れる前兆とは?
ギターの弦は突然切れるように思われがちですが、実はその前にいくつかの前兆が現れます。これらのサインを見逃さずに対処することで、弦が切れるのを防ぐことが可能です。
まず、弦の一部に変色やサビが見られる場合は、切れる前兆の一つです。特に金属製の弦は湿気や汗の影響で劣化しやすく、時間が経つと黒ずんだり、茶色くなったりします。この状態になると弦の強度が落ちており、負荷がかかった際に切れる可能性が高くなります。
次に、弦の特定の部分が異常に細くなっていたり、ささくれている場合も要注意です。これは、弦がナットやブリッジ、フレットなどの金属部分とこすれ続けることで摩耗している証拠です。特に、3弦や1弦などの細い弦は摩耗による影響を受けやすく、見た目では問題がなさそうでも、手で触ると違和感があることもあります。
また、チューニング時に異音がする場合も弦の寿命が近づいている可能性があります。通常、スムーズに巻き上げられるはずの弦が、チューニング時に「ギシギシ」「キュッ」という異音を立てる場合、弦が内部でダメージを受けていることがあります。この状態で無理にチューニングすると、急に張力に耐えきれなくなり、弦が切れることがあります。
最後に、弦の張りが急に弱くなる、チューニングが安定しないといった症状も前兆の一つです。弦が劣化すると、張力を一定に保つことが難しくなり、チューニングを合わせてもすぐに狂うことがあります。この場合、無理に張り直すよりも、早めに弦を交換する方が安全です。
このような前兆を見つけたら、弦を張り替えるか、少なくともその部分の状態をよく確認しておくことをおすすめします。
ギターの弦が切れる主な理由
ギターの弦が切れる原因はいくつか考えられますが、大きく分けると「弦の劣化」「弦にかかる負荷」「外的要因」の3つに分類されます。
まず、弦の劣化が最も一般的な理由の一つです。ギターの弦は金属製のものが多く、使用しているうちに摩耗したり、汗や湿気によって錆びたりします。特に、弦を長期間交換していないと、金属がもろくなり、わずかな張力の変化でも切れやすくなります。新品の弦よりも、使い古した弦の方が切れやすいのはこのためです。
次に、弦にかかる負荷が原因となることもあります。例えば、チューニングを頻繁に変える人は、弦の張力が繰り返し変化するため、通常よりも劣化が早まります。また、強いピッキングやチョーキングを多用する奏法では、弦にかかる圧力が増すため、特定の部分が摩耗しやすくなります。特に、ロックやメタル系の音楽で激しく弾く場合、弦が通常よりも早く切れることが多いです。
また、外的要因も無視できません。例えば、ナットやブリッジ、フレットにバリ(鋭くなった部分)があると、そこに弦が擦れ続けることで切れやすくなります。これは、新しいギターやカスタムしたギターに見られることがあり、ヤスリで微調整することで対策可能です。さらに、弦を巻く際にペグの巻き方が適切でないと、弦がねじれたり、部分的に負荷がかかることで切れることがあります。
このように、ギターの弦が切れる理由はさまざまですが、こまめなメンテナンスと適切な弦交換が最も効果的な対策となります。特に、定期的に弦の状態をチェックし、弦の張り方やギター本体の状態を整えることで、弦が切れるリスクを大幅に減らすことができます。
どこが切れやすい?弦が切れる場所の特徴
ギターの弦は、特定の場所が集中的にダメージを受けることで切れやすくなります。弦が切れる場所にはいくつかの特徴があり、それを理解することで予防策を講じることができます。
まず、ブリッジ付近は弦が切れやすい代表的なポイントです。ブリッジは弦を固定する部分であり、チューニングや演奏によって常に強い張力がかかっています。特に、ブリッジサドルに小さなバリ(鋭くなった金属部分)があると、弦が摩擦によって徐々に削られ、ある日突然切れることがあります。エレキギターではシンクロナイズドトレモロなどの可動式ブリッジを使用している場合、弦が頻繁に動くため摩耗が早まりやすくなります。
次に、ナット付近も切れやすいポイントの一つです。ナットは弦がペグへ向かう際に通る溝の部分であり、特に巻き弦(3弦や4弦)では摩擦が発生しやすくなっています。弦が切れる直前に、チューニング時に「ギシギシ」と引っかかるような感触がある場合、ナットが原因となっている可能性があります。ナット溝が狭すぎたり、長期間の使用で削れたりすると弦に負担がかかり、結果として切れやすくなります。
また、フレットと弦が接触する部分も摩耗によって弦が切れることがあります。特に、よく使用するポジションでは弦とフレットが強くこすれるため、弦が徐々に細くなり、ある日突然切れることがあります。チョーキングやビブラートを多用するギタリストは、特定のポジションの弦が極端に摩耗しやすいため注意が必要です。
最後に、ペグ周辺でも弦が切れることがあります。特に、弦を巻く際にねじれが発生したり、不適切な巻き方をしたりすると、局所的に強い負荷がかかることがあります。これにより、チューニング時に弦が急に切れるケースも少なくありません。
このように、弦が切れやすい場所にはそれぞれ特徴があり、定期的にチェックすることでトラブルを未然に防ぐことができます。ブリッジやナットのメンテナンスを怠らず、適切な弦の張り方を意識することが、弦の寿命を延ばすポイントとなります。
弦が切れるのが怖い…怪我のリスクは?
ギターの弦が突然切れると、その勢いで指や顔に当たることがあり、思わぬ怪我につながることがあります。特に、高音弦(1弦や2弦)は細くて鋭いため、切れた瞬間に手や目の近くにあれば、傷や刺さるような痛みを伴うこともあります。
最も危険なのは、弦が切れた際に目に当たるケースです。 まれではありますが、弦が跳ねる方向によっては目に直撃し、最悪の場合、視力に影響を及ぼすこともあります。そのため、弦交換時やチューニング時には顔を弦の真正面に近づけすぎないようにすることが重要です。
また、弦が指に当たって切り傷ができるケースもあります。特にチューニング中に弦が突然切れると、張力がかかっているため、弦の断端が勢いよく手に向かって飛んでくることがあります。鋭い金属片が指に触れると、軽い擦り傷や切り傷ができることがあり、痛みを伴います。
さらに、弦の切れた部分がギター本体を傷つける可能性も考えられます。特にアコースティックギターやクラシックギターの場合、ボディの表面に弦が勢いよくぶつかることで、小さな傷ができることがあります。これを防ぐためにも、弦を切れにくくする工夫が必要です。
安全対策としては、定期的に弦の状態をチェックし、劣化している場合は早めに交換することが最善策です。また、チューニングの際はゆっくりとペグを回し、無理に張りすぎないことも大切です。弦交換の際には、切れた弦の端が手や指に刺さらないように慎重に作業を進めることが安全につながります。
ギター初心者は弦を切りやすい?下手だから?
ギター初心者が弦を切りやすいのは、単に「下手だから」というわけではありません。むしろ、ギターの扱いに慣れていないことや、弦にかかる負荷を理解していないことが主な原因となります。
まず、過剰な力で演奏してしまうことが挙げられます。初心者は正しいピッキングやフィンガリングの感覚がまだ身についていないため、必要以上に強く弾いてしまうことがあります。特に、ピックを深く当てすぎたり、チョーキング時に無理な力を入れたりすると、弦に想定以上の負荷がかかり、切れやすくなります。
次に、チューニングミスも初心者が弦を切る原因の一つです。特に、オクターブ違いでチューニングしてしまうケースがあり、本来Eの音に合わせるべき1弦を、1オクターブ高く張ってしまうことで、弦が耐えきれずに切れることがあります。また、弦を交換する際にペグへ巻きつける方法が不適切だと、巻きの途中で弦がねじれ、負荷がかかることで切れやすくなります。
さらに、弦の寿命を把握していないことも影響します。初心者は弦を交換するタイミングを見極めるのが難しく、長期間同じ弦を使い続けてしまうことがあります。古くなった弦は金属疲労が進んでおり、ちょっとした衝撃やチューニングの負荷で切れやすくなるため、定期的に交換することが大切です。
このように、ギター初心者が弦を切りやすい理由は、技術的な問題というよりも、ギターの扱い方やメンテナンスに関する知識が不足していることが原因となる場合が多いです。正しいチューニングの方法を学び、適切な弦の張り方を覚え、無理な力をかけずに演奏することで、弦が切れるリスクを減らすことができます。
ギターの弦を切れにくくする方法

- 弦の寿命はどれくらい?
- 弦が切れにくいおすすめのメンテナンス方法
- 弦が切れたときの直し方と応急処置
- 切れにくいギター弦の選び方とおすすめ
弦の寿命はどれくらい?
ギターの弦の寿命は、使用頻度や環境によって大きく異なりますが、一般的には1週間~3か月程度が目安とされています。特に、毎日長時間演奏する人と、週に数回しか弾かない人では、弦の劣化スピードに差が出ます。
弦の寿命を決める主な要因の一つが酸化と腐食です。ギターの弦は金属製であるため、空気中の湿気や手汗によって錆びやすくなります。特に、湿度の高い環境で演奏している場合や、手汗が多い人は弦の劣化が早まり、1~2週間ほどで音質が低下し始めることがあります。一方、コーティング弦を使用すれば、通常の弦よりも寿命が長くなり、1~3か月程度使い続けることができます。
また、弦の摩耗も寿命に影響します。フレットとの接触によって弦がすり減ると、音の響きが悪くなるだけでなく、チューニングの安定性も低下します。特に、チョーキングやビブラートを多用する人は、弦がすぐに摩耗するため、こまめな交換が必要です。
さらに、演奏スタイルも弦の寿命を左右します。激しいピッキングをするロックやメタル系のプレイヤーは、通常よりも弦にかかる負担が大きく、消耗が早まる傾向があります。一方、ジャズやクラシックのように優しく弾くスタイルであれば、比較的長持ちしやすいです。
弦の寿命を延ばすためには、使用後に弦を拭く、弦交換のタイミングを見極める、適切な環境で保管するといった工夫が有効です。定期的にメンテナンスを行い、最適なタイミングで弦を交換することで、良い音質を維持しながら快適に演奏することができます。
弦が切れにくいおすすめのメンテナンス方法
ギターの弦を長持ちさせるためには、日々のメンテナンスが欠かせません。適切なケアを行うことで、弦が切れにくくなり、音質の劣化も防ぐことができます。ここでは、弦の寿命を延ばすためのメンテナンス方法を紹介します。
1. 演奏後は弦を拭く
弦は手汗や皮脂、ホコリなどによって劣化します。特に手汗には塩分が含まれているため、そのままにしておくと酸化が進み、サビの原因となります。演奏後は、専用のクロスや乾いた布で弦を拭き取る習慣をつけましょう。特にナット付近やブリッジ周辺は汚れが溜まりやすいので、念入りにケアすることが大切です。
2. 弦の交換時期を見極める
弦が錆びたり、チューニングが不安定になったりしたら、交換のサインです。一般的な弦の寿命は1週間〜3か月程度ですが、プレイスタイルや環境によって異なります。コーティング弦を使用すると、通常の弦よりも寿命が長くなるため、頻繁に交換するのが面倒な人にはおすすめです。
3. チューニング時の注意
無理に弦を引っ張ったり、過度にチューニングを上げたりすると、弦に大きな負担がかかります。特に初心者はオクターブ違いでチューニングしてしまい、必要以上に弦を張って切れてしまうことがあります。正しいチューニング方法を学び、無理な張力をかけないことが重要です。
4. 適切な環境で保管する
ギターの弦は湿気や温度変化に弱いため、保管環境にも注意が必要です。湿度が高い場所では弦が錆びやすく、乾燥しすぎると弦が劣化しやすくなります。ケース内に乾燥剤を入れたり、定期的に弦をメンテナンスすることで、長持ちさせることができます。
弦が切れたときの直し方と応急処置
ギターの弦が突然切れてしまうと、演奏を続けられなくなり焦ることもあるでしょう。しかし、正しい対処法を知っておけば、落ち着いて対応できます。ここでは、弦が切れた際の直し方と、すぐに交換できない場合の応急処置について解説します。
1. 切れた弦をそのままにしない
弦が切れたら、まずはギター本体や手を傷つけないようにすることが重要です。切れた弦の先端は鋭くなっているため、無理に引っ張ったりすると指を傷つける可能性があります。慎重にペグやブリッジから弦を外し、周囲に飛び散らないように処理しましょう。
2. 弦を交換する
理想的なのは、新しい弦と交換することです。弦交換の手順は以下の通りです。
- 切れた弦を完全に取り外す:ペグに巻き付いている部分やブリッジの穴に残っている部分をしっかり取り除きます。
- 新しい弦をブリッジに通す:アコースティックギターならブリッジピンを外して弦を差し込み、エレキギターならブリッジの穴に弦を通します。
- 弦をペグに巻く:適度な巻き数(2〜3回程度)を意識してペグに巻き付け、しっかり固定します。
- チューニングを行う:新しい弦は伸びやすいため、少し引っ張りながら音程を安定させるように調整します。
3. 応急処置としての対策
すぐに新しい弦が用意できない場合、以下の方法で一時的に対処できます。
- 弦の結び直し:切れた箇所がブリッジやペグの近くであれば、弦の端を結んで固定し、再びペグに巻き付けることで一時的に使用できます。ただし、音程の安定性が低下するため、長時間の使用には向きません。
- 別の弦で代用:予備の弦がない場合でも、ほかの弦を調整して使用することも可能です。例えば、6弦が切れた場合は5弦を6弦のチューニングにして演奏するなど、工夫次第である程度対応できます。
- 弦を張り直す:切れた部分が短い場合、ペグに巻き直して使えることもあります。ただし、弦の強度が落ちているため、再び切れる可能性が高くなります。
このように、弦が切れてしまった場合でも適切に対応すれば演奏を続けることが可能です。ただし、応急処置はあくまで一時的なものなので、できるだけ早く新しい弦に交換することをおすすめします。
切れにくいギター弦の選び方とおすすめ
ギターの弦は種類によって耐久性が異なります。頻繁に弦が切れてしまう人は、選び方を見直すだけで切れにくくなることがあります。ここでは、切れにくいギター弦の選び方と、おすすめの弦を紹介します。
1. 弦のゲージ(太さ)を選ぶ
弦の太さ(ゲージ)は、弦の耐久性に大きく影響します。一般的に、太い弦ほど切れにくく、細い弦ほど繊細な音が出せる反面、切れやすい傾向があります。
- ライトゲージ(0.010〜0.046):初心者にも扱いやすいが、力を入れすぎると切れやすい。
- ミディアムゲージ(0.011〜0.052):耐久性が高く、しっかりとした音が出せる。
- ヘビーゲージ(0.012~0.054):かなり太く、切れにくいが、押弦やチョーキングが難しくなる。
弦がよく切れる人は、ミディアムゲージ以上を試してみると改善される可能性があります。ただし、太い弦は指への負担が増すため、演奏しやすさとのバランスを考えることが重要です。
2. コーティング弦を選ぶ
ギター弦には、コーティング加工が施されたものと、そうでないものがあります。コーティング弦は、通常の弦に比べて耐久性が高く、汗や湿気による劣化を防ぐため、結果的に切れにくくなります。
特に以下のような人にコーティング弦はおすすめです。
- 手汗が多い人(錆びによる劣化を防ぐ)
- 頻繁に弦交換をするのが面倒な人(寿命が長い)
- 演奏頻度が高い人(耐久性が高い)
代表的なコーティング弦としては、Elixir(エリクサー)やD’Addario XTなどが人気です。通常の弦よりやや高価ですが、長期間使えるため、結果的にコストパフォーマンスが良くなる場合もあります。
3. 素材による違いを知る
ギター弦の素材も、切れにくさに関係しています。特にエレキギターやアコースティックギターでよく使われる素材には、以下のような特徴があります。
ニッケル弦(エレキギター向け)
柔軟性があり、比較的切れにくい。
初心者にも扱いやすい。
ステンレス弦(エレキギター向け)
耐久性が高く、錆びにくい。
指が滑りやすく、プレイアビリティが良い。
ブロンズ弦(アコースティックギター向け)
明るい音が特徴だが、酸化しやすく劣化しやすい。
コーティング加工があるものを選ぶと長持ちする。
フォスファーブロンズ弦(アコースティックギター向け)
通常のブロンズ弦よりも耐久性が高く、温かみのある音が出せる。
エリクサーなどのコーティングタイプと組み合わせるとより長持ちする。
切れにくさを重視する場合、ステンレス弦(エレキギター)やコーティングされたフォスファーブロンズ弦(アコースティックギター)を選ぶと良いでしょう。
4. おすすめのギター弦
上記のポイントを踏まえ、耐久性の高いおすすめのギター弦を紹介します。
- Elixir Nanoweb(エリクサー ナノウェブ)(コーティング弦、耐久性抜群)
- D’Addario XT(ダダリオXT)(バランスの良いコーティング弦)
- Ernie Ball Paradigm(アーニーボール パラダイム)(エレキ向け、高耐久)
- Martin Lifespan(マーチン ライフスパン)(アコースティック向け、高耐久)
ギターの弦は、演奏スタイルや好みによって適切なものが異なります。しかし、耐久性を重視するなら、太めのゲージ、コーティング弦、ステンレスやフォスファーブロンズ素材のものを選ぶと良いでしょう。適切な弦を選び、定期的なメンテナンスを行うことで、弦が切れるリスクを減らすことができます。
ギターの弦が切れる原因と対策
- 弦は金属疲労により切れやすくなる
- 演奏時の強いピッキングが弦に負担をかける
- チューニングの頻繁な変更が弦の寿命を縮める
- ナットやブリッジの摩耗が弦を傷つける
- 錆びた弦は切れやすいため定期的な交換が必要
- 低品質な弦は耐久性が低く切れやすい
- ブリッジやペグの鋭利な部分が弦を傷つける
- 湿気や汗が弦の劣化を早める
- 弦の張りすぎが過度な負荷をかける
- 適切なゲージ選びが弦の寿命を延ばす
- ストラップの高さが弦への力のかかり方に影響する
- 弦交換時にしっかりと巻かないと緩みやすい
- チョーキングやベンドを多用すると負担が増える
- ストリングワインダーの使用時は慎重に行う
- 弦の劣化を防ぐためにクリーニングが重要


