ギターのジャキジャキした音作りを実現するには、適切な機材の設定や演奏技術が欠かせません。特に、アンプのセッティングやエフェクターの活用によって、音の明瞭さやアタック感が大きく変わります。
例えば、ストラトキャスターを使ったカッティングプレイでは、中音域を適度に強調し、こもる音を防ぐ調整が必要です。また、BOSSのGT-1のようなマルチエフェクターを活用することで、多彩な音作りが可能になり、細かいニュアンスまで調整することができます。
音作りの勉強を進めるには、基本的な知識を学ぶだけでなく、実際に試行錯誤を重ねることが重要です。本記事では、ギターのジャキジャキした音作りを実現するための具体的な方法を詳しく解説していきます。
ギターのジャキジャキした音作りの基本とコツ

- ギターできれいな音を出すコツ
- 音作りの順番を理解しよう
- クランチサウンドとは?特徴と作り方
- ドンシャリサウンドの作り方
- ヴィンテージギターはなぜ音がいい?
ギターできれいな音を出すコツ
ギターできれいな音を出すためには、基本的な演奏技術を磨くだけでなく、機材の設定や演奏環境にも注意を払う必要があります。多くのギタリストは、アンプやエフェクターの設定ばかりに気を取られがちですが、まず重要なのは自分のピッキングやフィンガリングを見直すことです。
まず、ピッキングの強さや角度を一定に保つことが大切です。強く弾きすぎると音がつぶれ、弱すぎると輪郭がぼやけてしまいます。また、ピックを弦に対して適度な角度で当てることで、余計なノイズを抑えつつクリアな音を出すことができます。加えて、ミュート技術も重要です。不要な弦の共鳴音を抑えることで、よりきれいなサウンドになります。ブリッジミュートやフィンガーミュートを適切に使い分けることで、演奏の精度が向上するでしょう。
次に、適切なギターのセッティングを行いましょう。弦の種類やゲージ(太さ)は、音のクリアさに大きく影響します。一般的に、太めの弦は音にハリが出ますが、押さえるのが難しくなるため、自分の演奏スタイルに合った弦を選ぶことが重要です。また、ギターのピックアップの高さも調整することで、不要なノイズを減らし、音をクリアにすることができます。ピックアップが弦に近すぎると、磁力の影響で音がこもることがあるため注意しましょう。
さらに、音作りにおいてアンプやエフェクターの設定も無視できません。特にイコライザーの調整が重要で、低音・中音・高音のバランスを適切に設定することで、音がクリアになります。例えば、ミッドを少し持ち上げることで、音が前に出やすくなり、輪郭がはっきりします。また、リバーブやディレイを適度に加えることで、音の広がりを作ることも可能です。しかし、過度にエフェクトをかけると逆に音がぼやけてしまうため、細かい調整を心がけましょう。
最終的に、きれいな音を出すためには、演奏技術・ギターのセッティング・機材の設定を総合的に考えることが大切です。どれか一つだけにこだわるのではなく、すべての要素をバランスよく調整することで、理想のクリアなサウンドを手に入れることができるでしょう。
音作りの順番を理解しよう
ギターの音作りをする際に、適切な順番で設定を行うことは非常に重要です。順番を間違えると、音がこもったり、不自然になったりするため、基本的な流れを理解しておきましょう。音作りの順番は、大きく分けて「ギター本体」「アンプ」「エフェクター」の3つの要素を順番に調整することが基本になります。
まず、最初に見直すべきなのはギター本体の設定です。弦の種類やゲージ、ピックアップの高さ、トーンやボリュームの設定などが、音の基礎を決めます。ここで良い音が出ていない場合、その後のアンプやエフェクターで調整しても理想の音にはなりません。例えば、ピックアップの出力が高すぎると、アンプで歪みすぎたり、音がこもる原因になってしまいます。ギターのトーンを適度に開いた状態で、できるだけクリアな音が出せるように調整しましょう。
次に、アンプの設定を行います。ギターから出た音をどのように増幅し、どのようなキャラクターにするかを決めるのがアンプの役割です。ここでは、まずクリーンな音を作ることが重要になります。アンプのイコライザー(BASS・MIDDLE・TREBLE)のバランスを取ることで、基本の音色が決まります。例えば、ミドルを上げることでギターの音が前に出やすくなり、低音や高音を上げすぎると音がこもることがあります。クリーンの状態で音の輪郭をはっきりさせた後、歪みやエフェクトの調整に進みましょう。
最後に、エフェクターを加えて音のキャラクターを作り込んでいきます。エフェクターを使用する際も、適切な順番を守ることが大切です。基本的な順番として、コンプレッサー → 歪み系(オーバードライブ・ディストーション) → モジュレーション(コーラス・フランジャー) → 空間系(ディレイ・リバーブ)という流れが一般的です。特に、歪み系のエフェクターをかけすぎると音がつぶれてしまうため、アンプの歪みとバランスを取りながら設定しましょう。
音作りは「ギター本体の調整 → アンプの設定 → エフェクターの順番」の流れで進めることが基本です。順番を意識しながら調整を行うことで、よりクリアでバランスの良い音を作ることができます。
クランチサウンドとは?特徴と作り方
クランチサウンドとは、ギターの音が適度に歪みつつも、コードの輪郭がはっきりと聞こえるサウンドのことを指します。オーバードライブほど強く歪んでおらず、クリーントーンよりも力強さがあるのが特徴です。特に、ブルースやロックのリズムギターで多用されることが多く、ナチュラルな歪みを活かした温かみのあるサウンドを作ることができます。
クランチサウンドを作る方法はいくつかありますが、最も一般的なのはアンプのゲイン(歪み量)をコントロールすることです。アンプのボリュームを上げつつ、ゲインを低めに設定することで、自然なクランチサウンドを得ることができます。特にチューブアンプの場合、ボリュームを上げることでパワー管が程よく歪み、心地よいクランチサウンドを作ることが可能です。
また、エフェクターを使用する方法もあります。オーバードライブペダルを使ってアンプを軽くプッシュすることで、クリーンと歪みの中間のサウンドを作ることができます。このとき、エフェクターのゲインを低めに設定し、レベルを上げることで、より自然なクランチ感を得られます。
クランチサウンドは、ギターのボリュームコントロールを活用することで、より幅広い表現が可能になります。演奏中にギターのボリュームを絞ればクリーン寄りの音になり、開けばより歪んだサウンドになるため、細かいニュアンスを出すことができます。クランチサウンドを使いこなせば、楽曲のダイナミクスをより豊かに表現できるでしょう。
ドンシャリサウンドの作り方
ドンシャリサウンドとは、低音(BASS)と高音(TREBLE)を強調し、中音(MIDDLE)を控えめにしたサウンドのことを指します。ロックやメタルで多用されるサウンドで、パワフルかつシャープな音が特徴です。このサウンドを作るためには、アンプやエフェクターの設定、ギター本体の調整が重要になります。
まず、アンプのイコライザー設定から調整していきましょう。基本的なセッティングは、BASSをやや上げ気味にし、MIDDLEを下げ、TREBLEを高めに設定します。具体的な数値は使用するアンプによって異なりますが、例えば「BASS: 7 / MIDDLE: 3 / TREBLE: 8」くらいの設定にすることで、ドンシャリらしいメリハリのある音が作れます。ただし、MIDDLEを極端にカットしすぎると、音の抜けが悪くなり、バンドアンサンブルの中で埋もれてしまうことがあるため注意が必要です。
次に、エフェクターの活用も考えましょう。イコライザー(EQ)を使用することで、より細かい調整が可能になります。BASSとTREBLEを強調しつつ、MIDDLEを削ることで、ドンシャリサウンドを際立たせることができます。また、ディストーションやオーバードライブを使う場合は、歪みすぎると輪郭がぼやけることがあるため、ゲインは適度に抑えるのがポイントです。特に、ハイゲインアンプを使用する場合は、過度な歪みを避け、アタック感を意識すると良いでしょう。
さらに、ギター本体の設定も重要です。シングルコイルピックアップよりも、ハムバッカーのほうがドンシャリ向きの太いサウンドを出しやすい傾向があります。また、ギターのトーンコントロールを開き気味にすることで、高音域の抜けを良くすることができます。弦の選択もサウンドに影響を与えるため、ゲージの太い弦を使用すると、より太くパンチのあるドンシャリサウンドを作ることができます。
このように、ドンシャリサウンドを作るには、アンプのイコライザー設定を中心に、エフェクターやギター本体のセッティングも総合的に考えることが大切です。適切に調整を行うことで、迫力のあるパワフルなサウンドを手に入れることができるでしょう。
ヴィンテージギターはなぜ音がいい?
ヴィンテージギターは、現代のギターと比べて「音が良い」と評価されることが多いですが、それにはいくつかの理由があります。主に、木材のエイジング、製造技術の違い、ピックアップの特性などが関係しています。
まず、木材の経年変化(エイジング)が音に大きな影響を与えます。ギターのボディやネックに使用される木材は、時間が経つにつれて乾燥し、余分な水分や樹脂が抜けていきます。その結果、振動しやすくなり、音の鳴りが良くなるのです。特に、マホガニーやアルダー、アッシュなどの木材はエイジングによる音の変化が顕著に現れます。新品のギターと比べると、ヴィンテージギターはより豊かで奥行きのある音が出やすくなるのです。
次に、製造技術の違いも関係しています。1950〜60年代のギターは、職人の手作業による製造が多く、木材の選定や加工が非常に丁寧に行われていました。そのため、一本一本のギターが個性的な響きを持っており、現代の大量生産されたギターとは異なる音のキャラクターを持っています。また、当時の塗装方法も影響しています。ヴィンテージギターの多くはニトロセルロースラッカーという塗装が施されており、この塗装は木材の振動を妨げにくいため、音の鳴りが良くなると考えられています。
さらに、ピックアップの特性もヴィンテージギターの音を決定づける要素の一つです。1950~70年代のギターには、手巻きのピックアップが使用されていることが多く、現代の機械巻きのピックアップとは異なる独特の音色を持っています。特に、パフ(PAF)と呼ばれるハムバッカーピックアップや、ヴィンテージ仕様のシングルコイルは、温かみがありながらもクリアなサウンドを生み出します。
このように、ヴィンテージギターの音が良いとされるのは、木材のエイジング、製造技術の違い、ピックアップの特性などが影響しているためです。ただし、ヴィンテージギターはメンテナンスが必要であり、状態によっては音が悪くなっている場合もあるため、購入時には注意が必要です。
ギターのジャキジャキした音作りの実践方法
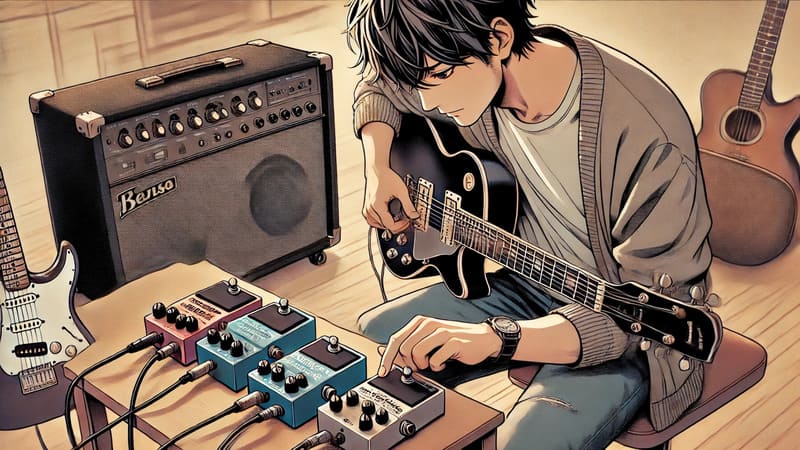
- アンプ設定で音作りを工夫する
- 音作りに役立つエフェクターの選び方
- GT-1での音作りのポイント
- ストラトでのカッティング音作りのコツ
- こもる音を防ぐための調整方法
- 音作りの勉強におすすめの方法
アンプ設定で音作りを工夫する
ギターの音作りにおいて、アンプの設定は非常に重要な要素です。同じギターやエフェクターを使っていても、アンプの設定次第で大きく音が変わるため、適切な調整を行うことで理想のサウンドに近づけることができます。
まず、基本となるのはイコライザー(EQ)の調整です。一般的に、BASS(低音)、MIDDLE(中音)、TREBLE(高音)の3つのつまみで音のバランスを決めます。たとえば、カッティングなどのリズムプレイを重視する場合は、中音域(MIDDLE)を強めに設定すると、音の抜けが良くなり、バンドの中でも埋もれにくくなります。一方で、ロックやメタルのようなパワフルなサウンドを作る場合は、BASSとTREBLEを強調し、MIDDLEを控えめにすると迫力のある音が得られます。
次に、ゲイン(GAIN)やボリューム(VOLUME)の調整も重要です。ゲインを高めることで歪みの量を増やすことができますが、上げすぎると音がつぶれたり、ノイズが増える原因になります。特に、クリーンサウンドを作りたい場合は、ゲインを低めに抑え、ボリュームを上げることで、よりダイナミックで抜けの良いサウンドを作ることができます。
さらに、アンプのリバーブ(REVERB)やプレゼンス(PRESENCE)を活用することで、音に広がりや明瞭さを加えることができます。リバーブを加えると空間的な響きが生まれ、よりナチュラルな音作りが可能になります。ただし、リバーブを過度にかけると音がぼやけるため、適度な調整が求められます。
アンプの設定次第でギターの音色は大きく変化します。自分の演奏スタイルや好みに応じて、イコライザーやゲイン、リバーブなどを細かく調整しながら、理想のサウンドを見つけていくことが大切です。
音作りに役立つエフェクターの選び方
ギターの音作りを細かく調整するためには、適切なエフェクターを選ぶことが重要です。しかし、市場には数多くのエフェクターが存在し、初心者にとってはどれを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。音作りに役立つエフェクターを選ぶ際には、自分が求めるサウンドやジャンルに適したものを理解し、最適な組み合わせを見つけることが大切です。
まず、エフェクターには大きく分けて「歪み系」「空間系」「モジュレーション系」「ダイナミクス系」などの種類があります。歪み系には「オーバードライブ」「ディストーション」「ファズ」などがあり、それぞれ歪みの特性が異なります。例えば、ブルースやロック向けの軽い歪みを求めるならオーバードライブが適しており、ハードロックやメタルのような強い歪みが必要な場合はディストーションやファズを選ぶと良いでしょう。
次に、空間系エフェクターとして「ディレイ」と「リバーブ」があります。ディレイは音を繰り返し反響させる効果があり、リードプレイに厚みを加えるのに便利です。一方、リバーブは音に自然な広がりを持たせ、演奏の雰囲気を豊かにします。ライブ演奏やレコーディングで、奥行きのあるサウンドを作る際に活用されます。
また、モジュレーション系エフェクターには「コーラス」「フランジャー」「フェイザー」などがあります。コーラスは音に厚みを加え、フランジャーやフェイザーは揺れやうねりを作り出すことで、より個性的なサウンドを生み出すことができます。
最後に、ダイナミクス系エフェクターとして「コンプレッサー」が挙げられます。これは音の強弱を整え、クリーントーンやカッティングを際立たせる効果があります。ただし、過剰にかけすぎると不自然になるため、適度な調整が必要です。
エフェクターは単体で使用することもできますが、組み合わせによってさまざまなサウンドを作ることができます。自分の演奏スタイルやジャンルに合わせて、必要なエフェクターを厳選し、最適なバランスを見つけることが、理想の音作りにつながるでしょう。
GT-1での音作りのポイント
BOSSのGT-1は、多機能ながらもコンパクトで使いやすいマルチエフェクターです。しかし、豊富な機能が搭載されているため、最適な音作りの方法が分からないという人も多いかもしれません。GT-1を効果的に活用するには、基本的な設定のポイントを理解し、目的に応じた調整を行うことが大切です。
まず、GT-1の音作りの基本となるのが「パッチ(プリセット)」の活用です。GT-1には多くのプリセットが用意されており、簡単にプロのようなサウンドを再現することができます。ただし、既存のパッチをそのまま使用するだけでは、自分の理想とする音と異なることがあるため、細かい調整を行うことが重要です。特に、アンプシミュレーターの設定を見直すことで、よりリアルで自然なサウンドに近づけることができます。
次に、エフェクトの順番を理解し、適切に配置することが大切です。GT-1では、コンプレッサーやEQ、歪み系エフェクター、空間系エフェクターなどを自由に並べ替えることができます。例えば、コンプレッサーを最初に配置すると音の粒が揃いやすくなり、歪み系エフェクターの前にEQを置くと、特定の周波数を強調することができます。また、リバーブやディレイなどの空間系エフェクターは最後に配置すると、音がクリアに響きやすくなります。
また、GT-1には「EZ Tone」機能があり、初心者でも簡単に理想の音作りを行うことができます。この機能を活用することで、各エフェクトの設定を細かく調整せずとも、ジャンルごとに最適なサウンドを手軽に作ることが可能です。
GT-1の音作りのポイントは、プリセットを活用しながらも、自分の好みに合わせて微調整を行うことです。エフェクトの順番や設定を工夫し、演奏スタイルに合ったサウンドを作り上げることで、より完成度の高い音を得ることができるでしょう。
ストラトでのカッティング音作りのコツ
ストラトキャスター(通称ストラト)は、カッティングプレイに適したギターですが、適切な音作りを行わなければ、音がこもったり、リズムのキレが悪くなってしまうことがあります。ストラトでのカッティング音を際立たせるためには、ピックアップの選択やアンプのセッティング、エフェクターの活用が重要です。
まず、ピックアップの選択が音のキャラクターを大きく左右します。ストラトには3つのシングルコイルピックアップが搭載されており、カッティングに適したポジションは「センター」または「センターとリアのハーフトーン(スイッチの2番または4番)」です。このポジションを選ぶことで、歯切れの良いサウンドを得ることができます。
次に、アンプの設定も重要なポイントです。カッティングプレイでは、BASSを控えめにし、MIDDLEとTREBLEを上げることで、シャープで抜けの良い音を作ることができます。特に、ファンクやポップスのカッティングでは、クリーントーンを基本とし、音がクリアに響くように調整すると良いでしょう。
さらに、エフェクターを活用することで、よりカッティング向けの音作りが可能になります。コンプレッサーを軽くかけると、音の粒が揃い、演奏が安定します。また、コーラスを少し加えることで、音に厚みを持たせることもできます。ただし、ディレイやリバーブを過剰にかけると音の輪郭がぼやけてしまうため、必要最低限の設定にすることが大切です。
カッティングプレイは、音作りだけでなくピッキングのニュアンスも重要な要素となります。適切なセッティングを見つけながら、リズムを意識した演奏を心がけることで、より洗練されたカッティングサウンドを作ることができるでしょう。
こもる音を防ぐための調整方法
ギターの音作りにおいて、「音がこもる」という問題は多くのギタリストが直面する課題の一つです。こもった音は、輪郭がはっきりせず、演奏のニュアンスが伝わりにくくなるため、しっかりと調整することが大切です。音のこもりを防ぐためには、主に以下の3つのポイントに注意する必要があります。
まず、アンプのイコライザー(EQ)設定を見直すことが重要です。特に、BASS(低音)が過剰に強調されていると、音がモコモコしてしまい、抜けが悪くなります。一般的に、こもった音を解消するためには、BASSを適度に抑え、MIDDLEとTREBLEを少し上げると効果的です。MIDDLEを適切に調整することで、音にハリが出て、バンドアンサンブルの中でも埋もれにくくなります。ただし、TREBLEを上げすぎると音が耳に刺さるようなキンキンした音になるため、適度なバランスを保つことが大切です。
次に、エフェクターの使い方にも注意しましょう。特に、コンプレッサーを強くかけすぎると音がつぶれてしまい、結果としてこもった印象を与えることがあります。適度な設定にしつつ、必要に応じて音量(レベル)を調整することがポイントです。また、空間系エフェクター(リバーブやディレイ)もこもった音の原因になりやすいため、過剰にかけないようにすることが大切です。特にライブ演奏では、リバーブを控えめに設定することで、音が前に出やすくなります。
最後に、ピッキングの強さや弦の状態も影響します。ピックのアタックが弱すぎると、音の輪郭がはっきりせず、こもった印象を与えてしまうことがあります。ピックの角度や力加減を調整し、しっかりとしたアタックを意識することで、クリアな音を出すことができます。また、古くなった弦は高音域の成分が失われ、全体的にこもった音になりやすいため、定期的に弦を交換することも重要です。
このように、アンプのEQ調整、エフェクターの適切な設定、そして演奏技術の見直しを行うことで、こもった音を防ぎ、抜けの良いサウンドを作ることができます。少しずつ試しながら、自分の理想の音を見つけていくことが大切です。
音作りの勉強におすすめの方法
ギターの音作りを深く理解するためには、基礎的な知識を身につけるだけでなく、実際に試行錯誤を繰り返しながら経験を積むことが重要です。しかし、どのように学べば効率的なのか分からないという人も多いかもしれません。音作りの勉強を進める際には、いくつかの方法を組み合わせることで、より効果的に知識を習得することができます。
まず、基本的な音響の知識を学ぶことが大切です。ギターの音作りは、単にエフェクターをつなげば良いというものではなく、周波数の特性や音のバランスを理解することで、より的確な調整が可能になります。そのため、EQ(イコライザー)の使い方や、アンプの特性についての知識を身につけることが重要です。書籍やオンラインの資料を活用して、音作りの理論的な部分を学ぶのも良いでしょう。
次に、実際の機材を使って試行錯誤することが欠かせません。アンプの設定やエフェクターの組み合わせを変えながら、どのような音になるのかを自分の耳で確かめることが大切です。特に、エフェクターの順番や組み合わせによって音が大きく変わるため、一つひとつの設定を細かく調整しながら試してみることが重要です。最初は既存のプリセットを参考にしながら、自分なりにアレンジを加えていくと、実践的な知識が身につきやすくなります。
また、プロのギタリストの音作りを研究するのも効果的です。好きなギタリストの音を再現することで、どのようなエフェクターやアンプの設定を使っているのかを学ぶことができます。最近では、YouTubeなどでプロの音作り解説動画が多く公開されているため、それらを参考にしながら、自分の機材で試してみるのもおすすめです。
さらに、音作りに関するワークショップやセミナーに参加するのも良い方法です。実際にプロの講師から直接アドバイスを受けることで、理論と実践の両方を効率よく学ぶことができます。楽器店やオンラインコミュニティで情報を集めながら、積極的に学べる場を探してみるのも良いでしょう。
音作りの勉強は、一度学んだら終わりではなく、常に新しい知識や技術を取り入れながらアップデートしていくことが大切です。基礎知識を学びつつ、実践と研究を重ねることで、自分にとって最適な音を見つけることができるでしょう。
ギターのジャキジャキした音作りのポイントとコツ
- ピッキングの強さと角度を一定に保つ
- ミュート技術を活用し不要なノイズを抑える
- 弦の種類やゲージを選び音の輪郭を調整する
- ピックアップの高さを適切に設定する
- アンプのイコライザーでBASS・MIDDLE・TREBLEを調整する
- クリーンな音を基準にアンプの歪みを設定する
- エフェクターの順番を意識し音を整える
- コンプレッサーで音の粒を揃えダイナミクスを調整する
- 空間系エフェクトを適度に使い音の広がりを演出する
- ドンシャリサウンドはMIDDLEを控えBASSとTREBLEを強調する
- クランチサウンドはゲインを抑えつつボリュームで歪みを作る
- ストラトのカッティング音作りにはセンターピックアップを活用する
- こもる音を防ぐには低音を控え中高音を調整する
- ヴィンテージギターは木材のエイジングとピックアップの特性が影響する
- 音作りの勉強にはプロの設定を分析し実践を重ねる


